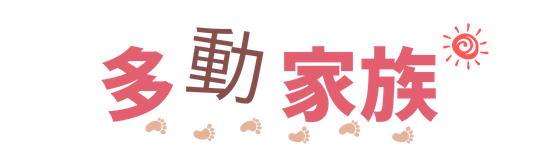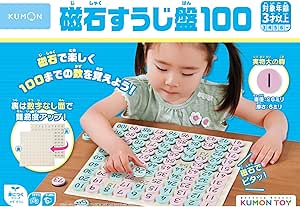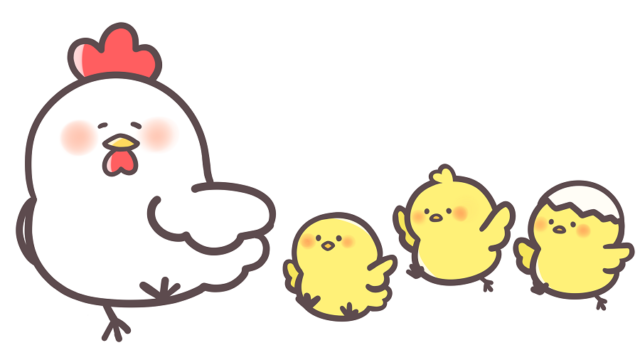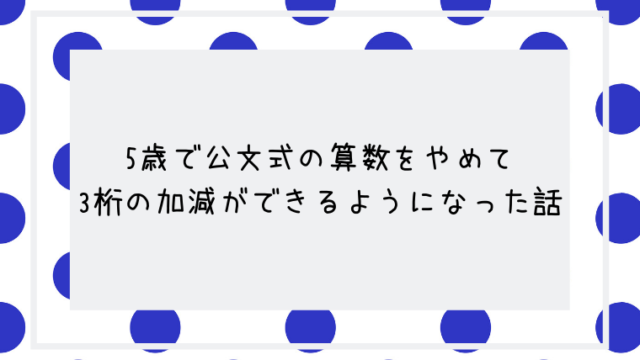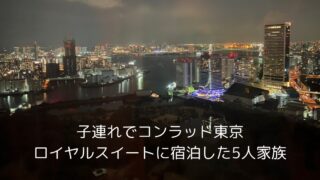こんにちは!小学6年生、3年生、1年生の3人を育てるワーママのぱわまむです。
「子供に朝勉強させたいけど、忙しい朝にそんな時間ない…」
「宿題すらやらせるので精一杯なのに朝学習なんて無理!」
「でも、勉強習慣はつけたいし…」
「いずれ受験するにあたって学力の基礎を鍛えておきたいけど、時間がない…」
そんなお悩み、ありませんか?
私はそうでした。
試行錯誤を繰り返し、一番は子どもたち自身の努力の成果ですが、今では見事に3人とも毎朝一定時間机に向かってそれぞれの勉強を進めるのが当たり前の習慣になりました!
小6の娘は中学受験を控えていることもあり、前日塾で遅くなるとなかなか朝起きられませんが、それでも毎朝最低20分。前日に塾のない日は30分ほど。
小3と小1の息子は、それぞれ50分と40分ほどの朝学習を毎日続けています。
しかも親が「勉強しなさい」と言わなくても、自分からやるようになっています。
今日は、共働きで多忙なご家庭でも無理なく続けられる「朝学習習慣化のコツ」をお伝えします。
同じように子供の学習習慣で悩む、教育熱心なワーパパさんワーママさんの参考になれば嬉しいです!
なぜ朝学習が共働き家庭にオススメなの?
朝学習の3つのメリット
1. 親の負担が軽い
朝は脳がクリアな状態なので、子供が集中してくれやすい
2.学習効果が高い
朝の方が記憶の定着率が良いと言われています
3.やるべきことを後回しにしないクセがつく
朝に勉強を済ませることができたら夜は自由に遊べるよ、と約束して習慣化することで、仮に朝終わらなければ、帰宅後キッチリ終わらせてから自由時間とする、という意識が定着しました。
実際、受験生の上の子の様子を見ていると、小さい頃からの勉強習慣が本当に力になって本人を支えていることがよくわかります。
ツラい時やサボりたい時ももちろんあるでしょうが、やるべき事を先に終わらせてしまった方が気持ちよく遊べる、と実感しているようです。
我が家の朝学習タイムスケジュール
6:20 起床
6:30 朝食・身支度
7:00 朝学習タイム
7:40〜50 出発準備
7:50 出発
ポイントは、朝食後のハッキリ覚醒した状態で勉強すること!
空腹だと集中できないし、起きてすぐだと頭が働かないんですよね。
ただ、休日になると謎に早起きすることのある子どもたち。
そんな日は、起きてまず最初に朝学習→準備が整ったら朝食、と順番が変更になることがあります。
お出かけの予定があったりすると、楽しみで早起き→早く出かけたいから起床後即勉強スタート!という思考のようです。
特に下の2人はよくコソコソと声を掛け合って勉強を進めていることがあり、面白いです。
【段階別】朝学習を習慣化する5つのテクニック
環境づくり(準備期間1週間)
1.「朝学習コーナー」を作る
家族構成や住居、子供の性格によって色々なパターンがあると思います。
我が家はさほど広くない家で3人分の勉強スペースを作るのにだいぶ苦心しました。
- ダイニングテーブルやリビングの一角を専用化
- リビングダイニングの空きスペースにコンパクトなデスクを設置
- 前夜に教材とえんぴつをセット
- タイマーも定位置に配置
「勉強する場所」が決まっていると、子供も自然に机に向かうようになります。
教材の準備は、今ではほとんど自分たちでやっていますが、はじめのうちはもちろん何をやるか親が主導して決めていかねばなりません。
なお、子供部屋ではなく、親の目が届くリビングやダイニングがオススメ!
家事をしながらでも見守れますし、わからないところがあったときにすぐ聞けると滞りにくいように思います。
ひとりでドンドン進めることができて、わからないところがあったら聞きに来るとか自分で調べるとかできる子なら子供部屋での勉強が向いていると思うのですが、我が家の子どもたちは全くこれに該当せず・・・
あと、他の兄弟もやっている、という状況が我が子達には勉強に向かいモチベーションとしてプラスに働いたようです。
2.教材は「簡単すぎる」レベルから開始
最初、張り切って年齢相当や少し上の問題集を買ったら「難しい!」と拒否反応が…
親バカフィルターで我が子は素晴らしく賢く思えますが、ここでの目的は先取りや難問への対応ではなく、あくまで学習習慣の定着。
割り切って、楽しくドンドン進められるような易しめの教材を選択することをお勧めします。
- 1学年下のレベルからスタート
- 1日1ページ(5〜10問程度)
- すぐ終わったからといって、予定分を超えてやらせない
- 「さすがだね!」「よくできてるよ!」などと自信をつけさせる
なお、我が家では基本的には公文式のプリント学習を行なっていますが、子供の希望や学習状況などを踏まえて、時々違う教材をはさむことがあります。
これまで取り組んだものは…↓
- ドラゴンドリル(息子がドハマリした傑作シリーズ)
- ポケモンドリル
- ピグマリオンの教材
- なぞぺー、チャレペー
- こぐま会ひとりでとっくんシリーズ
- 出口式論理国語シリーズ
- 天才ドリルシリーズ
- Z会グレードアップドリルなぞときすいり
机に座って鉛筆を動かすシリーズはこのあたり。
ドラゴンドリルがとにかくすごい。
当時小1男子の長男が、学校の参観日に好きなことを聞かれて「勉強!」と迷いなく答えたのは大変な驚きでしたが、まさにドラゴンドリルにドハマリしていた時期でした。
朝学習では飽き足らず、帰宅後も「ドラゴンドリルやっていい?」とどんどん進めてしまい、終わったら「早く次のを買ってほしい」と懇願されるような事態に。
ご褒美シールでドラゴン図鑑を完成させていく仕掛けが心の底から気に入ったようです。

小4文章読解のまき
中身は学研らしくクセのない定番の問題ですが、とにかく面白いぐらいのめりこんでいたので、低学年男子にはぜひ試してみてほしいと思います。
モチベーション作り(開始1〜2週間目)
3.朝学習の達成度を見える化して賞賛
定番は毎日1枚シールを貼ることでしょうか。
カレンダーに貼るもよし、100均などで台紙を買ってきてトイトレご褒美シールのように勉強できた日は好きなシールをペタリ!もよし。
我が家はオリジナルポイント制度を導入しました。
朝のうちに学習を終えることができたら1ポイント。
100ポイント貯まったら、ゲーセンで好きなゲームを1回とか好きな本を一冊、などと交換できる仕組みです。
朝学習以外でも、公文やスイミングの進級(各10ポイント)、学校イベントの頑張りなど、ポイントゲットの機会を多く用意して、ちょっとした楽しみにつなげています。
概ね100ポイントで500円相当で、1〜2ヶ月で100ポイント貯まるので、お小遣い制を導入していない我が家のお小遣い的位置づけでもあります。
物質なご褒美に変えることには賛否両論あろうかと思いますが、我が家では理由なく買い与えがちな夫と良いバランスに収まっています。
4.「できたね!」の声かけを大げさに
ここは私の反省点でもあります。
最初の頃はすごく意識していたのに、最近では学習をすること自体が日常になりすぎて、ついダメ出しが多くなりがちでした。
この機会に、当たり前かのように頑張っている子どもたちを盛大に褒める意識を取り戻したいと思います。
NGワード:
「もっと丁寧に書きなさい」「計算間違いしてるよ」
OKワード:
「わあ!今日も頑張ったね〜」
「毎日続けてるのすごいよ〜!」
完璧を求めず、「続けていること」「取り組んでいること」「机に向かっていること」を褒めるのがポイントですね。
習慣定着(3〜4週間目)
5.兄弟・姉妹で一緒にやる作戦
今のところ、年齢や内容の差はあっても、同じ時間の学習開始を目標に、全員に勉強させています。
兄弟効果は大変大きく、真ん中の子以降は学習習慣づけには正直さほど苦労しませんでした。
上の子がやっていると、それが当たり前という意識になるばかりか、「自分もやりたい!」となる子もいると思います。
そのタイミングを逃さず、机に向かう習慣をつけていきたいですね。
下の子が3歳で公文を開始するまでは、お絵かきタイムにしたり、公文の果物カードなどでクイズ形式で答えてもらったり(うるさくて上の子たちが気になってしまうので別室で)していました。
忙しいワーママでも大丈夫!時短サポート術
準備を夜のうちに
前夜チェックリスト:
□ 明日の教材を個別に準備
□ えんぴつを削っておく
□ タイマーをセット
□ 朝学習カレンダーとシール、ポイントカードとスタンプなどを用意
この4つで朝の準備時間がゼロになります。
タイマーは、よくあるキッチンタイマー的なものや、目で見えるタイマーなどいろいろ試してそれぞれ子どもが気に入ったものを使っています。
なるまでに終わらせるぞ!とか、鳴ったら学校の時間だよ、とか、わかりやすさが子どもにとっては大事なようです。
朝学習で変わった!我が家子どもたちの嬉しい変化
✅ 自主性がアップ
「勉強道具出しておくね!」と自分で準備するように
✅ 集中力が向上
徐々に集中して取り組める時間がのびていきます。
難しめの本なども集中して読めるようになってきました。
✅ 自信がついた
毎日コツコツ続けることは素晴らしいことだ、と繰り返し語って聞かせている影響もあると思いますが、「続ければ力になる」「自分はやれるし、やればできる」といった自信を身につけてくれているようです。
実家で親戚と集まった時には、年下のいとこ達に「いつものように勉強」する姿を見せては尊敬の眼差しを受けて、満足そうにドヤっています(笑)
年齢別おすすめ朝学習メニュー
年長さん以下(5〜20分)
- くもんのカードシリーズ(やさい、くだもの、動物など)
- くもんのマグネット数字盤
- モンテッソーリ教具
- ピグマリオン教材
- 紐通し
- ハサミを使う工作系のドリル
- 迷路、塗り絵
- タングラム系のパズル
- 間違い探し系のドリル
- 折り紙
- 数字の練習 1〜10
- ひらがな練習 2〜3文字
この時期はたくさん字を書くことや早く計算することなどより、「当たり前に知っていること」の範囲を増やすことや指先の巧緻性向上、図形や空間認識の強化、数量のイメージ化が優先ではないかなと思います。
教育系幼稚園や小学校お受験層なら当たり前に取り組んでいると思われますが、忙しい共働き家庭は多くが保育園での長時間保育でしょうし、家庭でコツコツ進めるしかないですよね。
計算や書字はいずれ成長とともに先取り学習勢と差がなくなっていくので、まずは色んなものに触れたり色んなことに挑戦したりする時間にしてあげられると良いのではないでしょうか。
小学1〜2年生(10〜30分)
- 計算系ドリル(ドラゴンドリル、ポケモンドリル、うんこドリル、ディズニープリンセスなど子供が好きな仕掛けやイラストがあると楽しくできる)
- カタカナ、漢字系ドリル(同上)
- パズル系、推理系ドリル(天才ドリル、なぞぺー、Z会など)
- 読解系ドリル(出口式など)
- 5分で読めるシリーズなどの読書
学校ですでに読み書きや計算は勉強しているので、学校の教材よりも興味を引くコンテンツを用意して、楽しく勉強できると良いと思います。
今後最も重要なのは読解力です。
中学受験以上になると、難易度が高くなるほどどの教科も長くて複雑な日本語で問題が書かれています。
問われていることが理解できないのでは、計算力や記憶力がどれだけあっても話にならないのです。
ファーストステップとして、まずは文章を読むことへの抵抗心をなくしていきたいところ。

天才ドリル 文章題が正しく読めるようになる どっかい算 (低学年版) (算数) 【小学校1~3年生向け】 (考える力を育てる)
出口式など丁寧に文章読解を解説してくれる教材も良いですし、読み物として次が気になる仕掛けのある推理系のドリルも良いです。

論理エンジン小学生版1年生: どっかい・さくぶんトレ-ニング

Z会グレードアップドリル まなべる なぞとき すいり 5-6歳
丁寧に問題を読むクセもつけられるとベストですね。
なお、公文式など計算の訓練をあまりしていない場合は、この時期にしておくと後が楽になると思います。
山本塾の教材、100マス計算シリーズあたりがオススメです。

5年生までにマスターする 山本塾の計算ドリル

<教育技術MOOK>陰山メソッド 徹底反復「百ます計算」
小学3年生以上(20〜50分)
- 計算ドリル
- 漢字練習
- 読解系ドリル
- 図形や文章題の算数ドリル
我が家のように公文式中心で学習していると、どうしても図形や文章題、思考系の問題には弱いです。
中学受験を検討するなら、ここを補う教材が必須になってきます。
ハイレベ最レベ、ハイクラス、算数ラボ、きらめき算数脳など、計算だけでなく思考系の問題が豊富なドリルも取り入れたいですね。

サピックスブックスきらめき思考力パズル 小学2~4年生 数センス特訓編
まとめ:小さな積み重ねが大きな力に
朝学習習慣化の5つのテクニック:
1. 朝学習コーナーを作る
2. 簡単すぎるレベルから開始
3. 朝学習の達成度を見える化して賞賛
4. できたことを大げさに褒める
5. 兄弟姉妹で一緒に取り組む
一番大切なのは「完璧を求めない」こと(と、自分に言い聞かせる!笑)
我が家も毎日完璧にできているわけではありません。それでも今、子供たちにとって朝学習は「当たり前の習慣」になっています。
忙しいワーママだからこそ、子どもの学習習慣づけが大事!
朝の時間を活用して子供の学習習慣を育てられれば、こども自身のためになるのはもちろん、私達親の負担も少し楽になる!・・・はず!