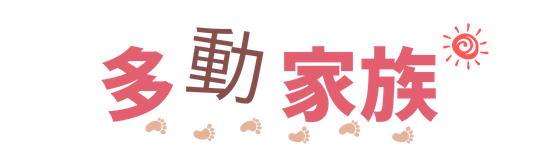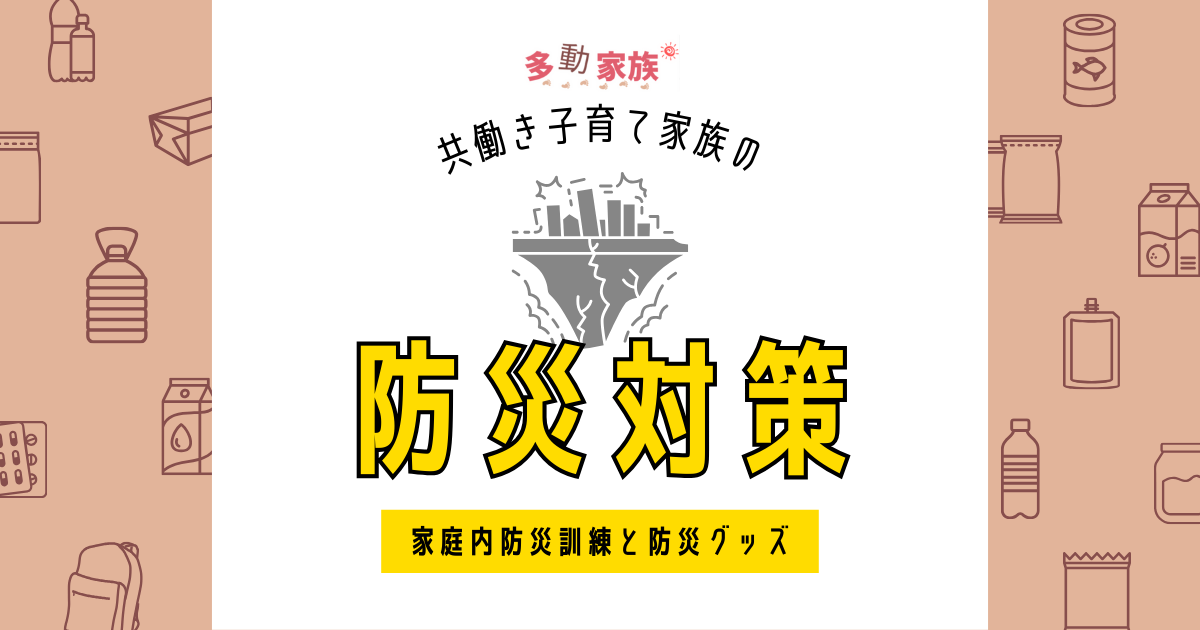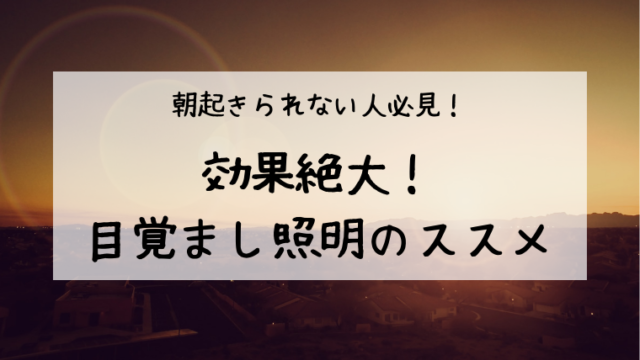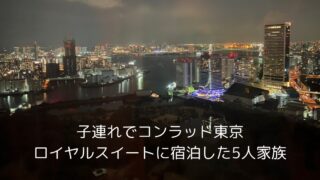日本は地震、台風、大雨、洪水などの自然災害が多い国です。
阪神・淡路大震災、東日本大震災、能登半島地震、そして高い確率で予想されている南海トラフ巨大地震に首都直下型地震。
特に小さな子どもがいる家庭では、災害のニュースを耳にするたびに、いざというときにどうやって子どもたちを守ればよいか、不安にもなることも多いと思います。
子どもは弱い生き物であり、大人が守らねば容易に危険に陥ります。
災害時の安全確保や避難の準備が大人以上に重要です。
いざというときに自分の身を自分で守れるように、知識と経験(+必要なグッズ)を与えておくことが重要ではないでしょうか。
しかし、実際には「何を準備すればいいのか分からない」「どこまで対策すれば十分なのか不安」と感じている方も多いのではないでしょうか?
我が家は小学生以下3人の子どもを育てる共働き夫婦であり、やはり離れている間に何かあったら、と思うと心配がつきません。
専門家の警鐘や自治体の広報など様々な情報を仕入れ、シミュレーションと家庭内訓練を繰り返し、定期的に見直しています。
この記事では、子育て世帯が行うべき防災対策と、いざという時に役立つ防災グッズについて詳しく解説します。
家族の安全を守るために、今からできる準備を進めていきましょう。
子育て世帯が行うべき防災対策
家族全員の避難計画を立てる
災害が発生した際に、家族がバラバラになってしまう可能性もあります。
特に、共働きだと親子が離れている時間も多く、事前の想定とシミュレーションが不十分だと、家族が合流することが困難になりかねません。
子どもが保育園・学校にいる場合や移動中の場合を想定し、避難計画を立て、約束事を決めておきましょう。
避難場所を決める
- 自宅での安全確保:在宅時に災害が起こった場合、どの部屋が安全か確認しておく(倒れやすい家具がない部屋など)。
大きな地震が発生した際、トイレやお風呂からは脱出しておくのが良いと言われますね。
扉が歪んで開閉できなくなる恐れもあるので、安全確保を優先しながらではありますが、揺れたら避難経路を確保しておくという意識が必要です。
- 指定避難所を確認:市区町村が指定する避難所を調べ、どこに行くか家族で共有する。
我が家の場合は、火災などで自宅に留まることが危険、という状況にならない限りは原則自宅待機です。
- 親が不在時の対応:子どもが学校などにいるとき、どこで合流するのか話し合う。
ここが一番心配なところですが、まず「大地震発生時にすぐには迎えに来れない可能性がある」ということを我が家では繰り返し伝えています。
夫婦ともに大都市で働いており、いわゆる帰宅困難者になる可能性があるためです。
子どもたちには「最悪3日かそれ以上時間がかかるかもしれないけれど、必ず迎えに行くから、学校や塾や保育園で先生たちと一緒に待っててね」と伝えています。
もちろんできる限り早く駆けつけたいですが、その後も被災者としての生活は続く可能性があり、焦って怪我したり二次災害に巻き込まれたりしてしまっては、結果的に子どもたちを危険にさらすことになってしまいます。
ですから、離れているときに大地震がおきたりした際には、まずは親が自分の身を守ることが最優先です。心配ですが、ある程度割り切りが必要だと考えています。
ところが問題はこれだけではありません。小学校高学年となった上の子は一人で自宅で過ごしていたり、一人で電車に乗って塾に移動したりすることがあります。
キッズケータイは持っていますが、いざというときは電話が繋がらないことをお互いに想定しておかねばなりません。
我が家は集合住宅で管理人さんが常駐しており、住民用の水等もある程度備蓄されているため、「困ったら管理人さんや他の住民の方に助けを求めるように」とも話しています。
子どもですから、緊急時には大人の助けが必要になることが当然あります。
素直に「助けて」と言える心の準備と、管理人さんや他の住民の方々と顔の見える関係を日頃から作っておくことを心がけています。
自宅の備蓄防災品の場所や使い方食べ方なども、年数回の家庭内訓練で少しずつ教えているところです。
連絡手段を決める
災害時は携帯電話がつながりにくくなる可能性が高いため、複数の連絡手段を想定しておくと良いと言われています。
- 災害用伝言ダイヤル「171」や「災害用伝言板(web171)」
練習しておかないとなかなか使いづらいので、学校や保育園などの引き取り訓練などに併せて練習しています。
- LINEやSNSでの連絡手段を決める
東日本大震災の際、電話は不通でもLINEやSNSでは連絡可能だった、というのは有名な話。
家族間で複数の連絡手段を持っておくことの重要性を感じます。
夫婦間で連絡が取れていれば、その後の動き方も考えやすいですしね。
- 遠方の親族を介して安否を伝える手段も持っておく
被災地周辺では電話が混み合って通じなくとも、地理的に離れた場所では問題なく通じるという場合があるそうです。
我が家の場合も、遠方の親族にひとまず安否や居場所だけでも伝えておくと、間接的にでも連絡が取れる可能性があることを子どもたちにも話しています。
- 公衆電話の使い方を練習しておく
大人には意外と盲点なのですが、今時の子供達は電話の使い方を知りません。
携帯電話がつながらない状況でも、公衆電話ならば通じるということもあるようです。
公衆電話を使って親の携帯電話に電話する練習をさせておく(電話番号を覚えさせたりランドセル等にメモを仕込む)こと、公衆電話から最低限連絡が取れるように小銭やテレホンカードを持たせておくこと、などを実践しています。
家の防災対策を強化する
災害発生時に家が危険な状態にならないよう、事前に対策を行いましょう。
- 家具の転倒防止
大型家具(本棚、食器棚、タンスなど)をL字金具や突っ張り棒で固定。
テレビや電子レンジなどの家電は耐震ジェルマットを敷いて固定。
寝る場所には倒れやすい家具を置かない。
このあたりが王道かつ優先度が高い対策ですよね。
我が家は賃貸なので壁に穴を開けて固定する方法は難しく、背の高い家具はできるだけ天井までのセミオーダーで設置しています。
それが難しい家具に関しては、耐震ジェルマットを愛用しています。
最近流行りの浮かせる収納は防災対策としても優秀なので良いですね。
- 窓ガラス対策
飛散防止フィルムを貼ることで、地震時のガラスの破片によるケガを防止。
カーテンを閉めることで、ガラスが割れた際の飛散を軽減する効果あり。
我が家はたいてい(ズボラで)カーテン閉めっぱなしですが・・・防災になるから良いということにしておきます。
- 非常用電源の確保
停電時のためにソーラー式の充電器やポータブル電源を準備。
ポータブル電源はアウトドア界隈でも人気ですよね。
夜間の避難に備えて懐中電灯やヘッドライトを手の届く場所に。
やはり電源と光が最も必要になるでしょう。
我が家は家のあちこちに懐中電灯を設置しており、家族全員分のライトを別に用意しています。
暗いなかで避難することになったときでも子どもを手をつなげるように、首掛け式のライトも用意しています。
家族の防災訓練を行う
防災グッズを備えるだけでは不十分で、実際に使い方を試しておくことが重要です。
薄暗く揺れが繰り返されて不安がつのるなかで初めて使うのはハードルが高すぎます。
防災グッズを実際に使用する訓練(懐中電灯や携帯トイレ、非常食など)。
子どもと一緒に「地震が起きたらどうするか?」を話し合う(例:「机の下に隠れる」「窓から離れる」)。
こうした訓練の繰り返しが安心につながってくれると期待しています。
子育て世帯が備えるべき防災グッズ(備蓄用品)
基本の防災グッズ(大人向け)
まずは、一般的な防災グッズを準備しましょう。
- 飲料水(1人1日2~3リットル×最低3日分)
- 常食(アルファ米、乾パン、缶詰、お菓子など)
- 携帯用充電器(モバイルバッテリー)
- 懐中電灯&予備の電池
- 簡易トイレ(最低1人1日5回分×3日分)
- カセットコンロとガスボンベ
- 救急セット(絆創膏、消毒液、常備薬など)
- 防寒具(ブランケット、カイロ、薄いダウンなど)
- 軍手、ホイッスル、マスク
- 給水ボトル(断水が長引いて給水車が来るときなどのため)
- 生理用品
- ラップ、使い捨ての食器
- アルコールウエットティッシュ
- ゴミ袋(ビニール袋)
- トイレットペーパー、ティッシュペーパー
- 整容品(ドライシャンプー、拭き取りボディタオル、拭き取り歯磨きなど)
- 現金、保険証コピー、連絡先一覧、地図
我が家は長期保存水を5人×5日分として70Lを目安に備蓄しています。
やや割高になりますが、自宅外に避難しなければならないときのことも想定して、2L容器だけではなく500mlボトルも用意しています。(2Lは運びにくいし重いので)
なお、長期保存水といっても保存期間は5年~15年と物によって異なるので、ご確認ください。
まめに更新するのが面倒な私は、安心の15年保存を選択。
日常的にボトルドウォーターを使うご家庭であれば、特に長期保存水である必要はなく、不通の水を多めにストックしておくぐらいで良いですね。
水の次に必要になると言われているのが簡易トイレ。
我が家はこちらも7回/日/人×5人×5日で約180回分備蓄しています。
こちらも安心の15年保存です。
食べ物は準備していてもトイレは忘れがちなので、ぜひ用意しておきましょう!
発災後最初の数時間以内にほぼ確実に必要性が出てくるのがトイレですからね。
非常食も5人分となるとなかなかの量ですが、ローリングストックしながら備蓄を減らさないように意識しています。
生鮮食品をとれないとタンパク質やビタミンが不足しやすそうなので、炭水化物ばかりにならないよう気をつけています。
とはいえ非常時はいつものように電子レンジなどは使えませんので、温かい食事ができるためのグッズも併せて用意。
カセットコンロとボンベは簡単ですね。ボンベをたくさん用意しておくと安心。
あとは火を使わないヒートパックも便利。
水を少量使いますが、食事を温め終わったら体を拭いたりするのに使えば無駄がありません。
万一子供だけが家にいるときには、これを使って温かい食事をとれるように教えています。
甘いものは緊張を和らげてくれますし、非常時にこそ食べられるように準備しておきたい。
食べた食器を水と洗剤でいつものように洗うことはできない前提で、使い捨ての食器を使うか、いつもの食器にラップを張ってラップを捨てればOK、と想定しています。
ラップは特別にというよりは普段使うものを気持ち多めにストックしているぐらいです。
水が出ないとシャンプーはおろか歯磨きもなかなか難しくなりますが、やはり子どもが小さいと衛生面は重要ですよね。
できる限り簡単に清潔を保てるように、ドライシャンプーや歯磨きシートを用意。
メリットのドライシャンプーシートは良い香りでお気に入り。
入院中にも便利なんですよね。
これは温めて使うこともできるので、寒いときはヒートパックに一緒に入れても、子どもに使ってあげたりしても良いかも。
これぐらいなら非常用持ち出しバッグに入れて避難所ででも使えそうです。
また、いざというときはキャッシュレス決済やマイナ保険証は使えないことを想定して、現金やアナログの情報も用意しておきます。
現金は一万円札だけだと使いづらいこともあるようなので、小銭や千円札も一緒に持っておきたいですね。
水濡れを避けたいので、防水のチャック付ビニール袋を活用します。
私と夫の非常用持ち出しバッグにそれぞれ入れています。
子育て世帯に必要な防災グッズ
子どもがいる家庭では、一般的な防災グッズに加えて、以下のようなものを準備すると安心です。
乳幼児向け
- 粉ミルク(キューブ型や液体ミルク)
- 哺乳瓶(使い捨てタイプも便利)
- 離乳食(レトルトタイプ)
- 紙おむつ、おしりふき、おむつ用ゴミ袋
- 抱っこひも(避難時に両手が空くように)
- 赤ちゃん用の防寒具(防寒着や帽子)
こどもの年齢によって備えるべきものが異なります。
幼児・小学生向け
- お気に入りのおもちゃや絵本(避難時のストレス軽減)
- 子ども用の非常食(クッキーやゼリー飲料など)
- 子ども用ヘルメット
- 迷子対策の名札(緊急連絡先を書いておく)
- 着替え(肌着・靴下を含めて3日分)
- タオル
- うわばき(スリッパ)
足元の備えは結構大事だと思っています。
もし悪天候で足元が濡れてしまったら辛いですし、ずっと外履きを履いているのも辛いですからね。
我が家の小学校高学年の子には、自分用の小さめ持ち出しバッグを用意しています。
最低限の水や食料、現金や連絡先などを入れています。
あとは、ユニクロのウルトラライトダウンなどを持ち出しバッグに入れておくのも良いように思っています。
GPSなどをつけておくのも良いかなと思いますが、通信が良くない状況ではあまり役に立たないかもしれませんね。
こういうときはおそらくアナログが最強です。
あとは、寒さ対策はできるのですが、暑さ対策は難しいところが最近の心配事です。
日本の近年の大災害って多くは寒い時期でしたしね・・・
まとめ:日頃の準備が家族の命を守る
子育て世帯にとって、防災対策は「いざという時に子どもを守るための投資」です。
家族全員の避難計画を立て、必要な防災グッズを揃え、定期的に家庭内訓練を行うことで、いざという時に慌てずに行動できます。
防災は「やりすぎる」ことはありません。
今日から少しずつ、できることから始めてみましょう!